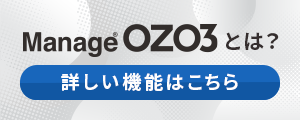- システム業
- 広告業
- クリエイティブ業
- イベント業
- 建設業
- 士業
- コンサルティング業
初心者でもわかる工数管理とは?工数管理のメリットと実施方法

働き方改革の推進で、テレワークが普及し始めたため、従業員がどのような仕事をしているのか確認しづらくなったと悩んでいませんか。
工数管理を行うことで、誰がどれくらいの仕事を持っているのか、1つのプロジェクトにかかっている時間がどれくらいなのかが明確にできます。
また、会社全体のプロジェクト毎の工数管理を行えば、利益が出ているプロジェクトと出ていないプロジェクトがわかります。
本記事では、これから工数管理を始める方や、工数管理に効果を感じていない方向けに、メリットや実施方法について紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
目次
工数管理とは?
工数管理とは、プロジェクトにかかっている業務時間を可視化させ、プロジェクトごとに労務費を算出できるようにすることです。
プロジェクトにかかった作業時間を明確にすることで、正確な労務費を把握することができます。
ただし、工数管理が必要な業種は、従業員の生産性が利益率に直結するシステム業や広告業などが対象です。
工数管理を行う業種は限られているため、自社の業種が工数管理を必要としているのかは、あらかじめ確認しておきましょう。
勤務時間と工数の違い
工数と勤務時間は別々に記録するものですが、厳密な原価を把握するために一致させて管理するのが望ましいです。
工数管理では労務費を見積もるために、勤務時間と工数が一致していることが重要になります。
例えば、工数と勤怠を別々の方法で記録している場合、勤務時間は1日8時間で記録されます。
一方で、工数の方は業務上でプロジェクトに携わった時間だけが入力され6時間になっている、といった差異が生じないようにしましょう。
プロジェクトに直接関わる業務ではない事前の準備や雑務などをしていた時間も、会社としては労務費がかかっています。
間接的な業務を工数として計算しないと、実際にかかっている原価からどんどんかけ離れてしまう点に注意が必要です。
工数管理で使われる3つの単位
| 工数の単位 | 単位の詳細 |
|---|---|
| 人時(にんじ) | 1人あたりの作業時間の単位 |
| 人日(にんにち) | 1人あたりの作業日数の単位 |
| 人月(にんげつ) | 1人あたりの1ヶ月の作業単位 |
工数管理において労務費は「かかった工数×時間単価」で計算されます。 単位は「人時」「人日」「人月」があり、例えば8時間勤務で1人が1日で完了できる作業の場合は、1人日となります。
このように、プロジェクトごとにどれくらい工数が生じているか記録し、かかわった人の労務費がいくらかかっているかを計算します。
工数管理はプロジェクトごとの利益を把握するために行う
- 外注費
- 材料費
- 経費
- 労務費
プロジェクトの利益は、受注額から上記4つの金額を差し引いて算出します。
このとき、労務費については、プロジェクトごとにかかった時間を管理していないと算出できません。
労務費の算出は、従業員ごとの給与とプロジェクトごとの工数を割って出します。
- 「原価の計算例」
- ●月給30万円の従業員が150時間働いた場合
- 30万÷150=時間単価2,000円
この場合、例えば150時間の内訳のうち、Aのプロジェクトに100時間かかっていたら労務費は20万円になります。
ただし、この計算方法は給与と労働時間が確定してから時間単価を算出する方法になりますので、月末に締めてからでないと算出できません。
リアルタイムで労務費を算出するためには、毎月の残業も加味して平均労働時間を割り出して、そこから時間単価を目安として設定しておく必要があります。
立場別で見る工数管理の目的
工数管理は立場によって目的や付けるべき工数の細かさが変わります。
会社として工数管理を導入する場合、高精度の原価計算をするために労務費を明らかにし、プロジェクトの収支を把握することが目的です。
取引先とプロジェクトごとに管理することで、利益率の見積の正確性が増します。
一方で、現場担当者として工数管理を行う場合は、どんな業務にどれだけの工数がかかっているかを把握し、業務効率化を図る目的があります。
無駄な工数や時間が生じていないかを見直すために、タスク単位まで細分化して工数を付ける必要があります。
会社目線で見る工数管理
会社目線の場合、工数管理を行う最大のメリットは、プロジェクトの採算を管理できることです。
工数管理によって正確な労務費を把握できれば、プロジェクトの利益がより正確にわかります。
そのためには、従業員ごとの「標準原価」を定めて、1時間作業したら労務費がいくらになるのか把握する必要があります。
標準単価の決め方は、役職に応じて「主任は時間単価2,500円」など、おおよその単価をあらかじめ決めておくものです。
単価を決めることで、工数がわかればおおよその原価も把握できるようになり、プロジェクトが赤字になっている場合にも早期改善が可能になります。
現場目線で見る工数管理
現場目線の場合は、スケジュール管理や業務効率化のために工数管理が必要とされています。
そのため、どのタスクにどれだけの工数がかかったか細分化された記録が必要です。
プロジェクトの進捗や工数を正確に把握できれば、リソースの確認やボトルネックの解消もしやすくなります。
また、工数をつけることでマネジメント層が評価しやすくなり、結果として従業員のモチベーション向上に繋がることもあります。
工数管理を「意味のないもの」にしないためには、しっかり採算を管理して従業員の評価をどんどん上げていける取り組みが必要になります。
工数管理を行う3つのメリット

- プロジェクトごとの利益率を把握できる
- 生産性の可視化や向上に役立つ
- 見積もり工数の精度が上がる
工数管理を行うことで、プロジェクトごとの利益を把握でき、生産性の可視化や見積もり工数の精度をあげられます。
さらに、業務状況が可視化ができるので、どうして赤字になっているのかといった課題点が明確になり、生産性向上に役立ちます。
また、工数の実績を正確に把握することで、次回以降の見積もり工数の予測ができるようになります。
プロジェクトごとの利益を把握できる
プロジェクトの利益は受注金額から原価を引くことで算出します。
原価のうち、外注費・材料費・経費は請求書や領収書などを記録すれば良いですが、労務費は工数管理を行わないと実態に近い金額はわかりません。
プロジェクトごとに生じた人件費を把握することで、正確な利益の算出ができるようになります。
利益が可視化されると、「売上金額は高額だったのに実は赤字だった」という事態を回避できます。
生産性の可視化や向上に役立つ
工数管理をすることで改善点が洗い出しやすくなるため、どのプロジェクトにどれだけの工数がかかっているか明確になります。
生産性を可視化することで、従業員の負担の軽減にもつながります。
工数がかかりすぎている部分を直接現場にヒアリングして問題点を把握できれば、早期改善につなげることが可能です。
プロジェクトの生産性が上がれば、結果的に売り上げや利益の増加にもなります。
見積もり工数の精度が上がる
工数管理のデータを蓄積していくことで、過去のプロジェクトと似たケースを扱う場合に高い精度で見積もりをすることが可能になります。
そのため、類似プロジェクトでの失敗予防にも役立ちます。
スケジュールや予算を感覚的に決めないようにすることで、進捗管理やコスト管理の見積が向上します。
その結果、納期の遅れやサービス品質の低下という問題も生じにくくなり、プロジェクトの生産性向上にもつながります。
もし、想定外の工数などが生じた場合も、工数管理で把握しておくことで、納期の調整などの対策を早急にすることができます。
工数管理をするためにはどんな方法がある?
工数管理をする方法は主に2つあり、「エクセルで行う」「工数管理システムを導入する」などがあります。
例えば、エクセルでの工数管理であれば、すでに導入している場合には費用はかからず、自社の使いやすいようにカスタマイズしやすいのが特徴です。
工数管理システムを導入した場合は、プロジェクト管理を一括でき、グラフでどのプロジェクトにどれだけ工数がかかっているか把握できるものもあります。
このように、工数管理を行う方法によってできることが異なるため、自社の予算や欲しい機能によって選ぶようにしましょう。
エクセルで工数管理をする
エクセルでの工数管理では、導入費用が最小限に抑えられるだけでなく、従業員も使い慣れているので比較的簡単に導入できます。
例えば、作成した工数管理表を共有フォルダに格納し、必要に応じて従業員が更新できるようにしておくだけで簡単に工数管理を行えます。
また、工数管理も好みにカスタマイズできるため、自由度の高い使い方をできるのがメリットです。
しかし、複数のプロジェクトを1つのエクセルで管理しようとするとファイルが重くなってしまうため、場合によってはプロジェクトごとに作成する必要があります。
その結果、複数のファイルを行き来して管理することになるため、管理業務が煩雑になってしまうというデメリットがあります。
エクセルでできる簡単な工数管理表
| 案件 | タスク | 予定工数 | 開始日 | 終了日 | 実績工数 | 工数差 | ABC株式会社 | システム構築 | 4/1 | 4/16 | 15 | 15 | 0 |
|---|
エクセルで工数管理を始める場合、まずは簡単に管理したい項目を作りましょう。 縦軸にプロジェクトや作業、横軸に日時や進捗状況などを設定し、必要な項目の値が分かりやすいように管理しましょう。
初めから記録する項目が多すぎると、入力や集計の手間がかかってしまうため、必要最低限の項目からスタートするのがおすすめです。
工数管理システムを導入する
工数管理システムでは、複数のプロジェクトを統合管理できます。
システムであれば、入力規則の設定や必須項目の設定などが行えますので、ミスや漏れを機能で防ぐことが可能です。
また、勤怠管理システムの1日あたりの労働時間から各プロジェクトにかかった時間を振り分けられるものもあります。
スマートフォンからでも管理しやすい製品もあるため、パソコンを使わずに工数管理を行えるのも工数管理システムのメリットです。
しかし、導入費用やランニングコストがかかってしまうため、導入前には複数の製品の見積もりを取得し、まずはトライアルから検討するようにしましょう。
入力や集計に困ったら工数管理システムの導入を検討
工数管理で集計・分析したい項目や人員などが増えて、管理が複雑になった場合には、エクセルより工数管理システムの利用がおすすめです。
工数入力に漏れが頻発したり、集計に時間がかかるうえ正確でなかったりする場合は、工数管理をしている意味がないため、早急にシステム導入を検討するのが良いといえます。
無料で使えるトライアル期間のサービスなどもあるので、上手く利用して自社にあった機能を搭載したシステムやアプリを見つけましょう。
初めてでもできる工数管理のやり方

工数管理を行う方法は、主に「工数表の作成」「実際の工数を入力」「工数の集計と改善を行う」の3ステップとなります。
まずは、管理者がプロジェクトごとに工数表を作成し、実際の工数を従業員が負担なく入力していけるように仕組みを構築します。
その後、従業員によって入力された工数の集計と改善を管理者が行い、結果に応じて軌道修正を行っていくのが基本の流れです。
ここからは、実際に工数管理を行う際の方法について、ステップごとに詳しくご紹介していきます。
Step.1工数表を作成する
- 管理者がルールを設定し、従業員が毎日入力しやすいものを作る
- スケジュールには、余裕を持たせて作成する
- 日報機能も追加し、従業員の声も聞けるようにする
工数表の作成は、ただ表を作るだけではなく、実際に入力する従業員が使いやすいものを作らなければなりません。
そのため、まずはプロジェクト管理者が工数表の入力方法やルールを設定し、入力する従業員のスキルやスケジュールに合わせて作成していきます。
また、工数表の導入は、進捗状況を可視化できるため、日報機能も合わせて追加しておくと良いでしょう。
その日の進捗と共に、実際の従業員の声を聞くことができれば、問題点や課題がより明確になります。
さらに、管理者からのフィードバックを受け取りやすくなるため、従業員のモチベーション低下を防ぐ効果も期待できます。
Step.2実際の工数を入力する
次に、作成した工数表へ、実際にかかった工数をできるだけ正確に、業務した日ごとに入力していきます。
例えば、8時間勤務した場合、8時間の内、プロジェクトのどの作業にどれだけ時間をかけたか割り振って入力を行います。
このとき、工数の入力方法は勤務時間ぴったりにする場合と、勤務時間より少なく見積もる場合があるので、事前にルールは決めておきましょう。
実際の業務では、8時間休まずに1つの業務を行うことはまず無く、従業員によっては複数のプロジェクトを掛け持ちしている場合があります。
そのため、管理者は従業員の作業進捗を把握し、負担の大きい業務を別の従業員に回すといった対策を取れるように、日々の工数管理を徹底しましょう。
Step.3工数の集計と改善を行う
最後に、管理者が工数の集計を行い、どのプロジェクトにどれだけ時間がかかっているか確認していきます。
このとき、工数管理システムを利用すれば、関わった従業員それぞれの時間単価とプロジェクトにかかった工数を照らし合わせられます。
そして、そのプロジェクトの利益率がどれくらいだったかを自動で算出できるため、集計作業を効率化できます。
また、完了していないプロジェクトの進捗をグラフや表で確認できるため、今後どのような改善が必要なのかも、ひと目でわかるように作られています。
そのため、集計作業を効率化し、改善に必要な状況をよりわかりやすく管理したいのであれば、工数管理システムの導入を検討してみてください。
工数管理を行うときに注意すべきポイント

工数管理はできるだけ精度の高い工数を入力することが大切ですが、工数を入力するために手間がかかるようでは、本末転倒です。
例えば、「工数表で管理しているプロジェクト内容が細分化しすぎている」「工数管理表の作成や入力に時間がかかっている」などがあります。
また、工数をつけるだけで終わってしまうと、従業員にとってはただの負担になってしまいます。
そのため、工数をつけることにより、正確に進捗状況を分析でき、より良くプロジェクトを進行できるといったメリットを見出さなければなりません。
工数管理は利益率を向上させるために必要不可欠
いざ工数管理を導入してみると、利益が出ていると思っていたプロジェクトが、実は赤字を出していることがわかる場合があります。
このように、工数管理を行うことで、採算の取れない業務を早期に発見し、改善していくことが可能です。
弊社の提供するOZO3工数では、プロジェクト別に工数を管理でき、工数原価推移表を使ってリアルタイムに状況を確認できます。
さらに、勤怠管理システムやワークフローシステムなどと連携を行えるため、勤務時間と工数を一元管理できるのも強みです。
また、スマートフォンからの工数入力もできるので、従業員の日々の入力を簡単に行えます。
無料トライアルを用意しているため、まずはどのようなシステムか知りたい方は、ぜひお問い合わせください。